折りたたみ式の電動自転車や、子供を乗せることができる電動アシスト自転車など、さまざまな製品が市場に流通しています。これらの呼称は似ているため、一見すると同じような乗り物だと誤解してしまうかもしれませんが、実際には異なる特性を持つ自転車です。
- 電動自転車と電動アシスト自転車の違いについて知りたい方
- どの自転車が自分に合っているのかわからない方や、購入を検討している方
- 法律や規制について把握したい方
- 豆知識として電動キックボードや電動スクーターについて興味がある方
これらの選択肢を検討する際には、どの自転車を購入するべきかのポイントをしっかりと把握しておくことが重要です。
静かに楽に走行できる電動自転車について、メリットとデメリット、さらに法令や規制について詳しく解説し、電動アシスト自転車との違いを明確にしていきます。
また、電動スクーターに関する規制についても情報を提供したいと思いますので、ぜひ参考にしてください。
フル電動自転車とは?種類や電動アシスト自転車との違い
近年、電動アシスト自転車は特に子育て中の家庭や高齢者にとって便利な移動手段として広く利用されるようになっています。
どちらの自転車も見た目は通常の自転車と変わりませんが、実際にはバッテリーを装備しており、軽くペダルを漕ぐだけでスムーズに進むことができるのです。
フルアシスト電動自転車
電動自転車の最大の特徴は、ペダルをこがなくてもアシスト機能が働く点です。
ペダルは存在しますが、自走機能があり、足を乗せているだけで自転車が前に進むことが可能です。
この自転車は原動機付き自転車に分類されるため、各市町村の役場に届け出を行い、ナンバープレートを取得する必要があります。
この自転車は時速30km/hまでのスピードが出ますので、歩道を走行することは許可されていません。
ペダルモード、アシストモード、電動バイクモードの3つのモード切替ができる点も特徴的です。
さまざまな制約があるため、購入を検討する際には、事前に注意すべきポイントをしっかりと調査することをお勧めします。
電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、通常の自転車と同様にペダルを漕ぐ必要がありますが、特に走り始めたときの負荷を軽減したり、坂道を上る際にアシスト機能が働くため、身体の負担を軽減しながら快適に自転車に乗ることができます。
取り扱いは一般的な自転車と同じですので、自転車に関する法規が適用されます。
電動アシスト自転車は、踏み込むと急加速することが特徴であり、アシストは倍の力を発揮し、時速10km/hまでの速度をサポートします。それ以上のスピードが出る場合には、アシスト機能は徐々に減少します。
フル電動自転車のメリットとデメリット
メリット
- 長距離移動が可能
- 身体への負担が少ない
- 膝の問題を抱える方でも利用できる
- 坂道や発進時が容易である
- 子供や重い荷物を乗せてもスムーズに走れる
- モード切替が可能な商品もあり、利用シーンに応じて選ぶことができる。
- 一方通行や歩行者専用道路でも、電源を切り手押しをすることで通行可能。
(原動機付き自転車のため、自転車のように乗ったまま一方通行道路を逆行することはできません) - 原付バイクよりも軽快に手押しできる
最も大きなメリットは、快適に速く移動できること、そして身体への負担が少ない点です。
デメリット
- バッテリーの充電や状態確認が必要
- バッテリーには寿命がある
- 価格が高額である
- 運転には免許が必要である
- 保険など維持費がかかる
- バッテリーが切れると非常に重く感じる
- サスペンションがない場合、道路の凹凸の影響を直接受ける
- 自転車モードでも、原付一種として扱われ、原動機付き自転車と同様の扱いを受ける
バッテリーが切れると、通常の自転車よりも重くなり、買い物の帰りにバッテリーが切れてしまうと、重い荷物とバッテリーの重さが加わり、非常に漕ぐのが困難になります。
坂道を漕いだり押したりする必要が出てくるのが、最大のデメリットです。
フル電動自転車と電動アシスト自転車の違い・道路交通法
フル電動自転車は・・・
- 運転には原動機付き自転車以上の免許が必要
- ヘルメットの着用が義務付けられている。
- 自賠責保険への加入が義務
- 保険は自動車保険のカテゴリーに分類される。
- ナンバープレート取得のために役所に車体番号を届け出る必要がある
- もちろん歩道を走行することは違反となり、罰則があります。
- 種類によっては、原動機付き自転車と同じ制限速度の30kmまで出るモデルも存在する。
- 灯火や速度計の整備に関しての違反も罰金の対象となる可能性がある
- 原付バイクと同様で、バッテリーが切れるとウインカーやライトが点灯しなくなり、取り締まりの対象になることがある
- 右折時は自動車と同じ右折レーンで待つ必要があり、3車線以上の場合は二段階右折が必要
アシスト自転車は・・
- 人力よりも強いパワーで動くことはないように制御されている。
- 自転車として扱われるため、保険加入の義務はない
- イヤホンを使用して運転してはいけない。
- ヘルメットは義務ではないが、頭を守るために着用することが推奨される。
- 最大で2倍のアシストが可能だが、漕ぐ力は必ず人の力が必要となる。
- 自転車と同じルールが適用され、左側通行、一時停止、歩道では徐行などが求められる。
もちろん、人と衝突して怪我をさせてしまったり、事故を起こすと、賠償責任が発生することがあり、財産に対して支払えないほどの請求が来る可能性もあります。
見た目が自転車だからといって軽視せず、保険に加入していない場合や、免許なしでの運転は絶対に避けなければなりません。
豆知識<電動キックボード・電動スクーターとの違い>
街中でしばしば見かけるのが、小型の電動キックボードです。

街中でシェアされている電動キックボードは、『小型特殊自動車』に分類されており、速度が15km/hまでに制御されているため、免許が必要ですがヘルメットの着用は義務ではありません。
個人が所有する場合は、『原動機付き自転車』に分類され、免許とヘルメットの着用が必要です。
2023年以降に道路交通法が改正される見込みがあり、電動キックボードや電動キックスクーターは、特定小型原動機付き自転車に新たに分類される予定です。
個人所有のものは原付バイクに分類されていたのが、自転車寄りの新たなカテゴリとなります。
最高速度が20km/h以上のものは『原動機付き自転車扱い』となり、最高速度がそれ以下の製品は新たな分類の『特定小型原動機付き自転車』として扱われることになります。
規制が緩和され、通常は自転車道または自動車道を走行することが可能ですが、速度が6km/h以下であれば、歩道を走行することも許可されるようになります。
| 個人所有 | シェア業者 | ||
| 現行 | 最高速度 | 30km/h | 15km/h |
| ヘルメット | 必要 | 不要 | |
| 免許 | 原付免許 | 普通自動車免許 | |
| 歩道走行 | ❌ | ❌ | |
| 改正後 | 免許不要・ヘルメット着用努力義務 最高速度20km/h 歩道走行❌(最高速度6km/h以下であれば⚪) | ||
個人所有とシェア業者でルールが分かれていたものが統一され、ヘルメットの着用も努力義務となり、免許不要で利用しやすくなります。
ただし、基本的には車道を走行することになりますので、曲がる際には歩行者や自動車に注意する必要があります。
今後、電動キックボードや電動スクーターがより多くの人に利用されるように、4輪の製品も販売されることで、安全性の向上にも期待が寄せられています。
フル電動自転車は買ってはいけない?のまとめ
電動自転車と電動アシスト自転車は、名称が非常に似ているため、混同してしまう方も少なくありません。
免許を持っていない方は、電動自転車を購入してはいけないのです。
特に小学生や中学生など、家庭に電動自転車があるからといって軽い気持ちで乗ってしまうことがないよう、しっかりと話し合いを行い、鍵の管理を徹底することが重要です。
通常の自転車は大変かもしれませんが、その分脚力が付き、骨盤周りの引き締めや、ダイエット全般にも非常に効果的ですので、ぜひ検討してみてください。

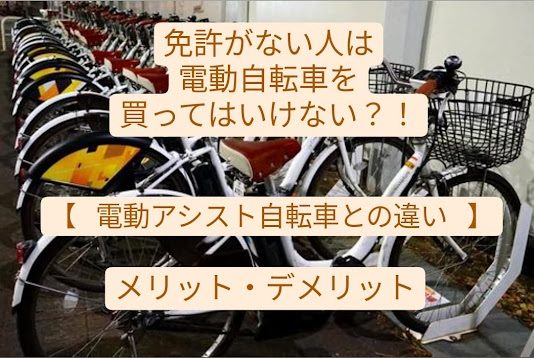


コメント